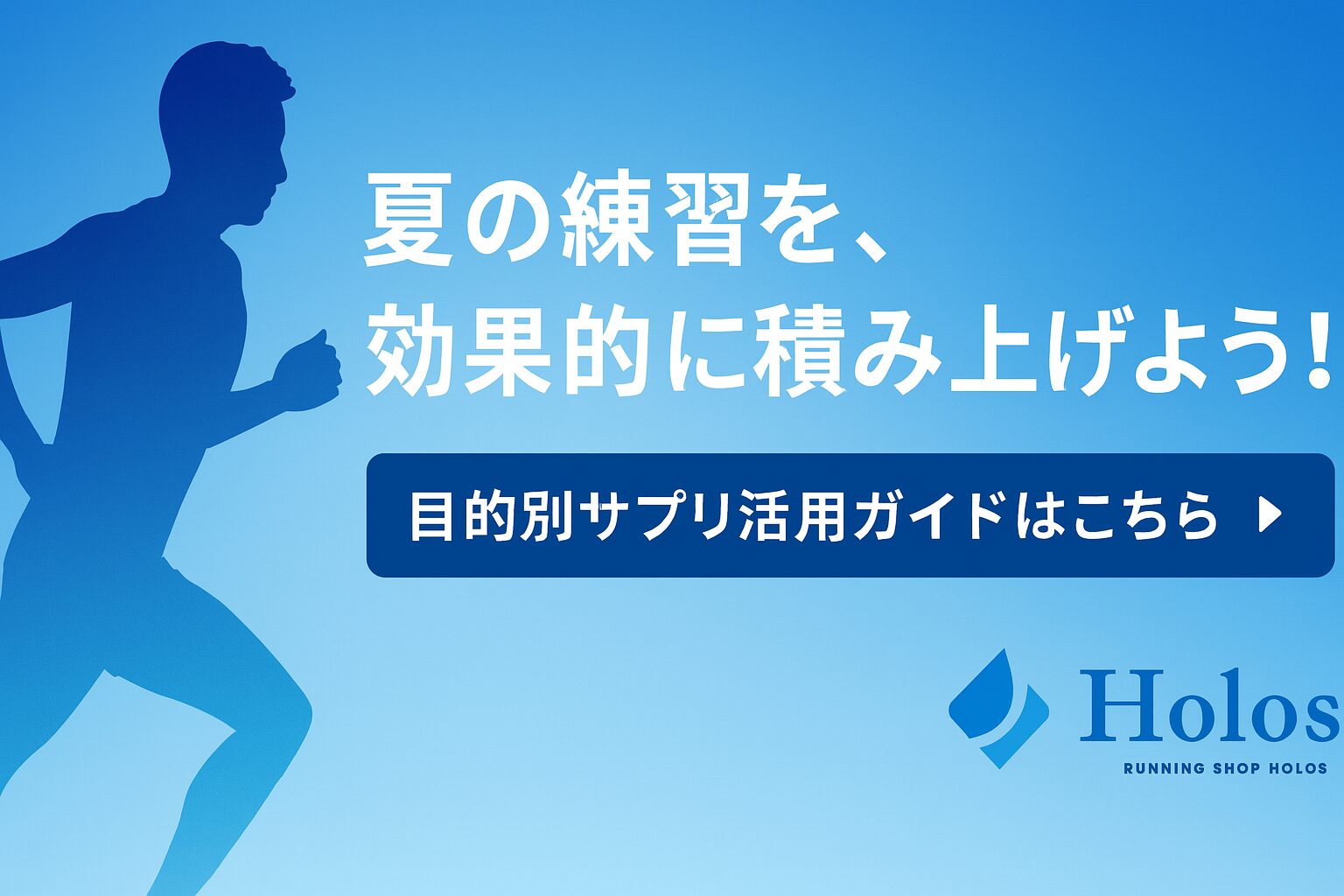こんにちは。
ランニングショップHolosの小谷です。
今回は記録向上を目指す戦略の中でも最も大事な要素の1つである「大会までの練習計画の作り方」について一緒に考えていきたいと思います。
皆さんは練習メニューをどのように考えていますか?
昔、ランニングの練習会を開催した時に参加者の方に聞いたところ
- 【60%】練習メニューをとくに考えず、何となく走っている(自分なりのルーティンはあるが、特に根拠などは無い)
- 【30%】ネットや書籍のメニューを基本的に真似して、生活に合わせて少し調整している
- 【10%】色々な情報を収集して、自分の頭で考えてオリジナルなものを作っている
という感じでした。
これは決して市民ランナー全体を表している比率ではありませんが、練習会に参加するくらいモチベーションのある人たちでも、練習メニューについて積極的に考えている人は少ないのだなぁと驚いたことがあります。
マラソンで実際に記録を出すためには、頭で考えるのではなく、実際に頑張って練習することの方が大切であることは間違いありません。
ただ、その頑張りをより効率的に結果につなげていくには、やはり良い戦略というものが欠かせないと私は思います。
また、こうした戦略を自分なりに色々と調べて考えることは、マラソンの知的な楽しみの1つでもあります。
今回は私の24時間走世界選手権を目標にした練習計画を事例にして「大会から逆算したメニューの作り方」について紹介していきます。
どの種目でも役立つよう一般化した知識としてお伝えしますので、皆さんの記録向上&メニュー作りの楽しみにお役立てください。
「現状・残り期間・過去のデータ」の3つの視点で分析する

私が大会までの練習計画(3~6か月くらいの期間を想定)を作るとき、まず最初にすることが下記の3つの視点で状況を分析することです。
- 現状:直近2~3か月の練習データを見直し、現在地を確認します。
- 残り期間:大会までの残り日数によって、どれだけ成長できるかが変わります。鍛える能力の取捨選択も迫られるでしょう。
- 過去のデータ:現状と残り期間が分かれば、経験者なら、おおよその目標や達成プロセスが推定できるものです。ここに過去のデータ(とりわけ成功時のデータ)があれば、より精度の高い計画作りができ、確信をもって実行へと移せるでしょう。
以下に、それぞれの項目を詳しくみていきます。
1.現状を把握することで着実な次の一歩が踏み出せる
現状把握においては以下の3つの項目に注目すると良いでしょう。
※練習に関しては、直近2~3か月くらいの期間を見返すのがおすすめです
- 練習負荷はどうだったか(負荷=距離×スピードです。ボリュームが多い練習、ハードなスピード練習は負荷が高くなります):
1週間の平均的な週間走行距離、その中のスピード練習の割合などをチェックします。負荷が急に上がると故障リスクが増すため、「今の自分はどれだけの練習に耐えられるのか」を理解するためにも、直近の練習状況とはきちんと向き合う必要があります。 - 練習の内容:ロング走が中心だったのか? スピード練習が多かったのか? スピード練習の内容は? ウルトラが目標なら1回でまとめて長く走る練習の実施状況は?
- コンディションや生活の課題など:痛み箇所、体の不調など気になることはあったか? 生活のストレスなど今後練習を頑張っていくにあたって解消していきたい課題はあるか?
私の事例(7月初旬の自己分析)
私の直近3か月の練習は負荷は以下の通りでした。
| 月 | 週間の有酸素運動時間(分) | 耐久力(※) |
|---|---|---|
| 4月 | 250分 | 44 |
| 5月 | 340分 | 79 |
| 6月 | 525分 | 113 |
※耐久力について。私は時計はポラールを使っていますが、その中に耐久力という項目があります。これは、「直近4週間の有酸素運動の負荷」を表しています(ボリュームだけでなく、ペースの速さも考慮された値)。
4月の「44」という値は、4月末時点で「44」レベルの負荷の練習を4週間継続できていたことを示します。他メーカーさんの時計のことは詳しくないのですが、おそらく「トレーニング負荷」の項目がこれに近いものだと思います。
私は2~3月と夫婦関係でトラブルがあり、すっかり落ち込んで練習が思うようにいかない日々が続いていました(今は解消したのでご安心を!)。
4月からようやくリハビリのようにランニングを再開し、3か月たった6月末時点ではだいぶ自信も取り戻している状況でした。
この通り、4→6月はブランクからの再開なので通常より早いペースで練習負荷を上げることができましたが、ここからは「慎重に増やしていかなくてはいけない」と自覚するようにします(1か月でプラス10%くらいが目安)。
5~6月のスピード練習は(1分 疾走+1分 jog)×20のような疾走区間が短くて速いスピード練習を中心にしていました。
心肺機能に適度な負荷をかけつつ、筋肉・神経系も刺激して速い動きにも慣れてきたことで1000m×5~10本のようなロングインターバルにも体がついていく準備ができていることが確認できました。(この確認が、後述する7月からのスピード練習の内容に影響してきます)
2.大会までの残り日数を確認し、練習の取捨選択をしていく

現状についてのイメージが固まったら、次は大会までにどれくらい練習ができるのか、残り日数を確認します。
私が目標を世界選手権に定めたとき、大会までの残り日数(週数)は16週間でした。
私はだいたい3~4週間を1つのブロックとして、ブロックが変わるごとに1週間の練習メニューに変化を加えていくという方法をとっています。
今回は以下のようにブロックを分けて、各ブロックに目的を持たせることにしました。
| 月 | 練習内容・テーマ |
|---|---|
| 7月 | 心拍ゾーン4~5のスピード練習を中心にして、ジョギングのペースを上げる。余裕度を高めることに集中した期間(※) |
| 8月 | ウルトラに向けたロング走を開始(1回か2回)。まずは5時間~の練習に心理的な抵抗をなくすため、ゆっくりペースでOK。平日のスピード練習は少し比重を落としながら継続(減らした分はジョグのボリュームをアップ)。 |
| 9月 | 5~6時間の心拍ゾーン3(中~上)での「そこそこ速いペースでのロング走」を最重要ポイント練習に。平日のスピード練習も高速ジョグの感覚にして練習全体をレースペース域に近づけていく。 |
| 10月 | 9月の練習の延長&適度に疲労を抜いて大会へ。 |
※このようにスピード→ロングという期分けについては別ブログ『100kmウルトラに向けたスピード練習|夏に実践したいベースビルディング法』でもご紹介しました
紙に書くなどして、残り期間を明確にすると、できる練習の回数に限りがあることが分かります。
これは単純なことですが、とても大きな価値があることなので、ぜひ行動に移していただきたいです。
例えば
- ウルトラが目標の場合、ウルトラ用のロング走(50km~)の枠を早めに確保できます(慌てて直前に詰め込むと故障のもとですし、体調の問題などで回数をこなせないリスクがあります)
- スピード練習が大事と思っていても、いざ書き出してみると4セッションくらいしかやる時間がないことに気づくかもしれません(スピード練習をきちんとするなら、できれば6~8セッションは枠を確保したいところです)
といった発見につながるでしょう。
3.過去の成功時のデータと比較すれば、より再現性のある自信を持てるメニューに
現状分析と大会までの残り期間が確認できれば、経験者ならおおよそのゴール地点(目標タイム)とそこへ至る道筋(練習計画)がうっすらと見えてくるものです。
そこに、比較できる過去のデータがあれば、ロードマップはより鮮明に浮かび上がり、自信をもって計画を実行しようという気持ちも湧いてきます。
過去の成功時のデータを分析するときは
- そのときに、直近の2~3か月でどのような練習負荷をこなしていたか?
- 直近2~3か月の有酸素運動の時間
- その競技に専門的なポイント練習の内容と回数(ウルトラの場合なら50km~のようなロング走。フルマラソンなら、レースペースに近いペースでの20~30km走など)
に注目すると良いでしょう。
今回の私のケースでは、去年の台湾での24時間走(自己ベスト264km)の練習データが比較対象となりました。
2024年東呉国際ウルトラマラソンの練習データ
週間の有酸素運動時間:770分
耐久力:120
主なウルトラ専門のポイント練習:
大会の3~8週間前の期間で合計4回の60~70km走。心拍ゾーン3(中~上)。
このデータから、私は
- 自己ベスト更新を狙うなら、これと同等の練習はしたい→直近2か月の週間運動時間は770分程度、耐久力120
- ロング走は60~70km程度で良いので、「楽に速く」で4回は実施
- 現時点から大会までの残り期間で、この練習に追いつくことは可能だろうか? → 可能!!
といったことを考えていました。
過去のデータを持ち出すことで、ゴールまでのストーリーが明確になり、自信とエネルギーが湧いてくるというメリットが感じられるはずです。
また、故障リスクを伴うあまりにも無計画な練習などは避けやすくなり、良い意味で現実的にもなれると思います。
実際にできあがった私の7~10月の練習計画
①現状、②残り期間、③過去の成功データの3つの視点で分析し、情報を整理していった結果、以下のようなトレーニング計画を立てました。
| 月 | 位置づけ | 概要 |
|---|---|---|
| 7月 | ジョグのスピードを上げるための下準備期間 | 週間の有酸素運動時間:700~730分 耐久力:120~130 |
| 8月 | ウルトラ向けロング走のための下準備期間 | 週間の有酸素運動時間:770~820分 耐久力:130~140 |
| 9月 | ウルトラ専門練習を強化 | 週間の有酸素運動時間:820~880分 耐久力:140~150 |
| 10月 | ウルトラ専門練習の続き&調整 | 週間の有酸素運動時間:820~880分 耐久力:140~150 |
このような大枠が決まれば、あとはそれを1週間のメニューに落とし込むという流れになります。
私の7月の週間メニューについては、以下のブログのメニューサンプルのところで公開していますので、興味のある方は合わせてご覧ください。
『【レベル別メニュー付き】夏のマラソン練習は分割&負荷調整で着実に積み上げる』
計画作りのポイントとしては、以下の3点をおさえておくと良いでしょう。
- 各ブロック(今回の場合は月ごと)の目的を明確にすること
- 全体的な負荷の推移が無理なく、かつチャレンジングなものになっていること
- 最重要なポイント練習に向けて、段階を追って準備ができていること(今回の場合は60~70km走を楽だけど速く走れるようになっていること)
まとめ(チェックシート用意しました)
以上が私が世界選手権に向けて作った練習計画の概要でした。
情報量が多くなってしまいましたので、以下に作成のために役立つチェックシートをご用意しました。
pdfにしていますので、よろしければ印刷して参考にしてみてください。
▼練習計画チェックシート(3ステップ)のダウンロードはこちら
良い戦略は、目標達成というゴールまでの効果的なルートを示す地図のようなものです。
ぜひ皆さんも時間をとって、紙とペンを用意して、ゴールまでの道筋を描いてみてはいかがでしょうか。
今日もお読みいただき、ありがとうございました!
夏の暑さに負けず、練習を積み重ねたいあなたへ
▶︎ 目的別サプリ活用ガイドはこちら【夏のトレーニング編】