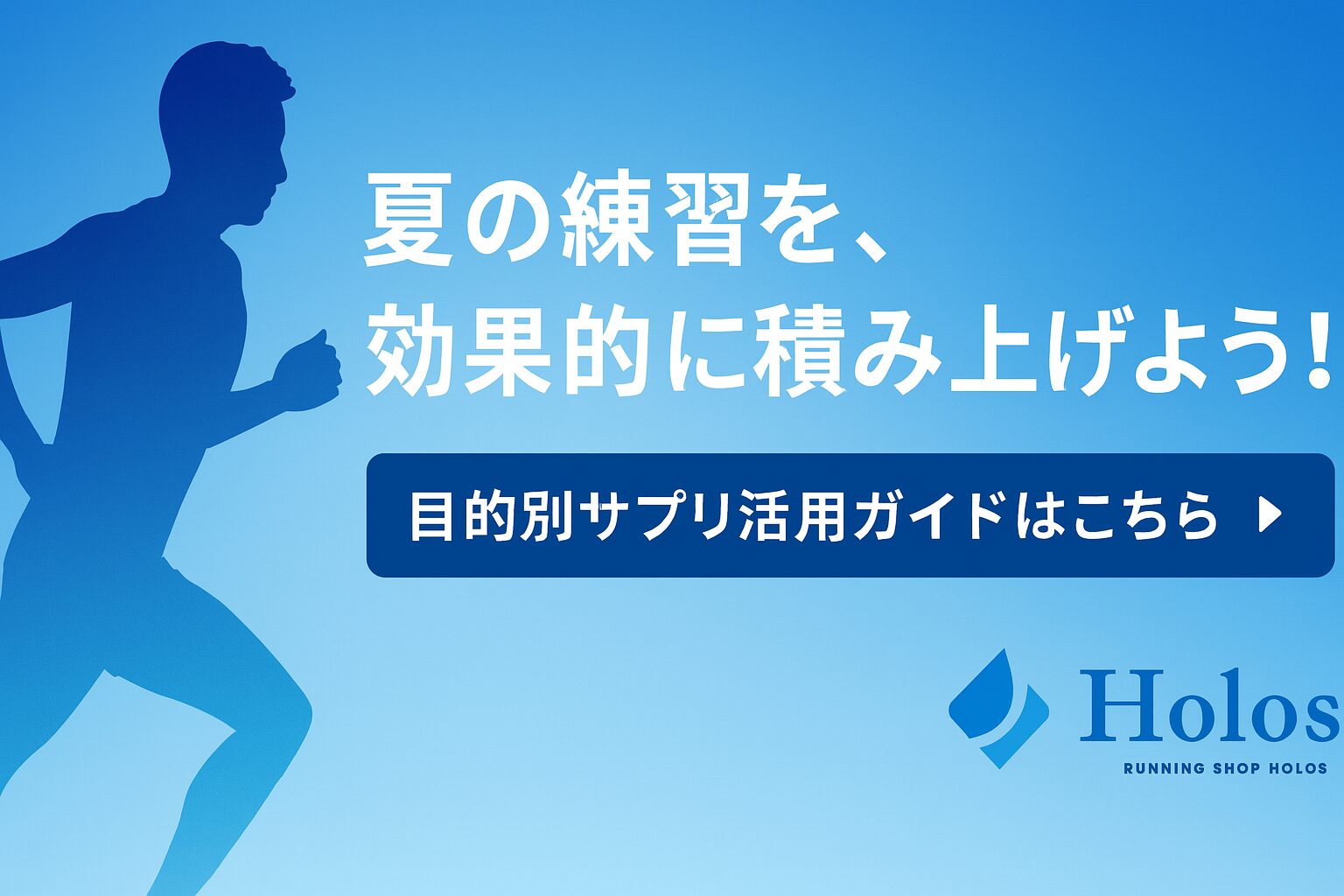こんにちは。
ランニングショップHolosの小谷です。
今日も前回に引き続き「夏のトレーニングを成功させて、秋から例年以上の記録を狙えるようになろう」というテーマで考えていきたいと思います。
前回は「暑さ慣れすることで、夏でもパフォーマンスが低下しにくい=練習を維持しやすい体質を作ろう」というアイデアを紹介しました。
-

-
暑さに強くなる練習法|夏のランニングに効く暑熱馴化のやり方
こんにちは。 ランニングショップHolosの小谷です。 7月に入り、ますます暑さが厳しく走るのが大変になってきましたね。 「本当はもっと頑張りたいのに、暑くてどうにもならない」とお悩みの方も多いのでは ...
続きを見る
今回はその次のステップ。『暑さに慣れたとはいえ、やっぱりキツい夏』をどう乗り越え、トレーニングを継続するか。そのポイントを整理していきます。
秋のレースで結果を出すために、今できる「潰れにくい工夫」を一緒に考えていきましょう。
ペースよりも心拍数や主観的な強度により注目する

まずはトレーニングにおいて私が意識していることからシェアしていきたいと思います。
1つめは、ペースに固執せずに心拍数や主観的な強度の方をより注意深く観察しながら練習をするということです。
これは、夏は気温によってパフォーマンスが大きく変化するからです。
日によって気温・湿度が変わりますので「先週まで走れていた練習が今日は相当きつい」と感じることもあるでしょう。
このとき、ショックを受けて意欲を低下させてしまったり、無理に以前のペースに追いつこうとしては練習の狙いを達成できなくなってしまう可能性がでてきます。
大会が近くなってきたころには特にレースペースを意識して、その近いペースで走ろうと心掛けるのは良いかもしれませんが、夏の段階からその日のペースに一喜一憂していては精神的にも消耗してしまいます。
なので、今の時期はペースに気をとられすぎないことが大切だと思います。
私は個人的には「この練習で成長スイッチが押される程度の刺激を与えよう」と意識すると上手くいくように感じています。
絶対的なペースが遅くとも、心拍数がきちんと狙いのゾーンのあたりまで上昇していたり、主観的なキツさが想定したくらいに達していれば、体にはきちんと刺激が加わっています。
その刺激がある程度の時間加われば、体の成長スイッチがオンになり、休んでいる間に体が強くなっていくことをイメージします。
このように考えることで、ペースに固執した焦り、意欲低下、練習の失敗を防ぎやすくなると思います。
体温の急激な上昇や高体温が長時間維持される練習は潰れやすいので避ける
夏の練習で潰れてしまう理由の多くは「体の深部体温が上昇しすぎて危険にさらされる前に脳がストップをかけるから」だと考えられます。
これは中枢性疲労と呼ばれるメカニズムで、体温上昇が脳の安全装置を作動させるからだと言われています。
途中で潰れてしまった練習に効果が全くないわけではありませんが、せっかくなら十分に体に刺激を与えて、精神的にも「今日も頑張れた」と充実した気持ちになりたいですよね。
そのためには「この練習では自分の体温はきちんと安全な範囲に収まると脳を説得することができるだろうか?」と考えるのがコツです。
例えば、30分間を「キツい」~「かなりキツい」と感じるペースで走る練習は、夏場では潰れやすい厳しい練習だと思います。
これは涼しい時期でも厳しい練習であることに間違いはないのですが、さらに夏場では
- 体温が急激に上昇しやすい(ペースが速い)
- 高体温状態が維持されてしまう(インターバルのように途中で発熱が収まるタイミングが無い)
という体温調整上の厳しさも加わってきます。
よって、私なら夏場はこのようなペース走は避けてインターバルにしたり、更に柔軟性を持たせたファルトレク形式にしてしまいます。
例えば
- 15分 ウォームアップジョグ
- (5分 疾走 + 2分 ジョグ)×6本
- 10分 クールダウンジョグ
のようにしたら失敗リスクをぐっと抑えることができます。
周回コースにしてジョグのときに給水&水かけもできれば更に安定性が増すでしょう。
インターバルにしてもペースは30分を続けて走った場合から速くする必要はありません。
レスト区間があると「楽になって効果が減ってしまうのでは?」と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、練習的には「ある強度でどれだけの時間を走れたか」が重要になりますので問題はありません。
大会が近づいてきたころには「レースペースに近いペースでレースの60~70%くらいの距離を連続で(レスト無しで)走る」というようなレースに類似した練習も大事にはなってきます。
しかし、今はまだ大会まで期間のある方も多いでしょうし、練習の安定性アップのメリットの方が大きいと考えて良いと思います。
レスト区間は「心拍数チェック」と「歩き」でさらに練習に安定性を

上記のように練習のインターバル化(ファルトレク化)を意識するだけで夏の練習はグッと負荷を維持しやすくなると思います。
さらに練習の安定性を高める方法はレスト区間の心拍数をチェックするという方法です。
レスト区間が終わり、疾走区間に入ろうとするタイミングで心拍数がどれだけ落ち着いているか(下がっているか)によって、その後の疾走区間をきちんと走れる確率が変わってきます。
例えば、私は最近ファルトレクで「400m×10」のような疾走区間があるときは、疾走区間に入る直前までに心拍数が150bpm以下に下がっていたら、まず潰れないので安心という目安があります。
この目安は心拍数を意識しながら練習を何度か繰り返せば、自分なりの感覚が分かってくると思います。
目安が分かると練習中も「よし、心拍数がきちんと落ち着いたから、次の疾走区間も安全にいけるぞ」と自信がわいて、精神的にも楽になります。
この「安心ライン」は人によって違います(あと、続く疾走区間の質によっても変化します)。
ぜひ何度か試して、自分なりの潰れない心拍数を見つけてみてください。
なお、夏は暑さのせいで、後半は心拍数が全然下がらないこともあります。
そのときは、レスト区間に「歩き」を入れてみるのもおすすめです。
きっとジョグより早く体内の状態が回復して次の疾走区間に備えることができると思います。
セッション単位で練習を分割する(高頻度で練習する)
ペース走(連続で走る)をインターバル(分割して走る)に修正したように、これをセッション単位で分割してしまうという方法もあります。
例えば20kmのロングジョグを朝10km、夜10kmの2部練習にしてしまうということです。
2部練習にすることで、1回心身をリフレッシュすることができますので集中して練習できますし、当然途中で潰れてしまうリスクも軽減できます。
私は以前「24時間走で264kmを達成した練習のポイント」というブログで「練習頻度を高めるようにしたら上手くいった」という話をしました。
今も昔と比べて「高頻度」の練習を意識しています(1回1回の練習は以前より短い)。
なので、「2回に分けたら楽になって効果が減るのでは?」という心配もそこまでしなくて良いと思います。
特に今の時期は分割して、途中で休憩を挟みながら全体の練習負荷をできるだけ維持しようと試みることが結果につながる姿勢だと私は思っています。
クロストレーニングで有酸素運動の時間を稼ぐ
これは環境が許せばですが、クロストレーニングも夏場は特に有効だと感じています。
室内バイクでしたら外より快適な温度で運動ができますし、屋外でも自転車は風の冷却作用のおかげかランニングよりも快適に運動することができます。
ちなみに7月の私の個人的な練習計画では、クロスバイクによるトレーニングを週に3回(各40~60分程度)入れています。
1週間全体での有酸素運動の時間が約700分なので20%くらいをクロストレーニングにあてている計算です。
夏のトレーニングメニューのサンプル

最後にここまでの内容を踏まえた、夏でも練習負荷を維持しやすい1週間の練習メニューのサンプルをいくつかご紹介します。
人それぞれ目標や課題意識に違いがあると思いますので、サンプルを参考にしながら自分なりに修正を加えて、自分にあったメニュー作りをしてみてくださいね。
秋フルに向けたベースビルディング(週間300分)
| 曜日 | 内容 |
|---|---|
| 月 | 50分 jog |
| 火 | 40分 jog |
| 水 | 60分 ファルトレクA |
| 木 | 40分 jog |
| 金 | 休息日 |
| 土 | 60分 ファルトレクB |
| 日 | 50分 jog |
| メニュー名 | 内容 |
|---|---|
| ファルトレクA | 25分 ウォームアップjog (1分 疾走 + 1分 jog)×10 15分 クールダウンjog |
| ファルトレクB | 25分 ウォームアップjog (3分 疾走 + 2分 jog)×4 15分 クールダウンjog |
大会までまだ期間のある今は、疾走区間は短めのスピード重視で。
今のうちに速い動きに慣れておき、涼しくなってから「速い動き維持するため」のより長い疾走区間のファルトレクへと移行。
秋100kmに向けたベースビルディング(余裕度向上目的 週間420分)
| 曜日 | メニュー |
|---|---|
| 月 | 60分 ファルトレクA |
| 火 | 60分 jog |
| 水 | 70分 jog |
| 木 | 70分 ファルトレクB |
| 金 | 休息日 |
| 土 | 90分 jog |
| 日 | 70分 jog |
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| ファルトレクA | 20分 ウォームアップjog (1分 疾走 + 1分 jog)×6 +(2分 疾走 + 1.5分 jog)×4 15分 クールダウンjog |
| ファルトレクB | 25分 ウォームアップjog (4分 疾走 + 2分 jog)×4 20分 クールダウンjog |
9月下旬~10月の100kmが目標なら、今はジョグのスピードを上げるためのスピード練習ができる期間でもあります。
大会が近づいてきたら、ロング走をより重視し、スピード練習も「レースペースのジョグより10~20秒/km速いペース」の30~60分間走などへ移行していきます(より長く、遅いペースのスピード練習へ)。
小谷の今年の7月計画(ウルトラベースビルディング 週間725分)
| 曜日 | メニュー |
|---|---|
| 月 | 70分 ファルトレクA |
| 火 | 80分 jog 夕方:55分 自転車ファルトレクB |
| 水 | 80分 jog 夕方:40分 jog |
| 木 | 75分 ファルトレクC |
| 金 | 80分 jog 夕方:45分 自転車ファルトレクD |
| 土 | 80分 jog+40分 自転車 (easy) ※1回でまとめて実施 |
| 日 | 80分 jog |
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| ファルトレクA (ラン) |
20分 ウォームアップjog (40秒 疾走 + 1分 jog)×4 + (3分 疾走 + 2分 jog)×6 15分 クールダウンjog |
| 自転車ファルトレクB | 10分 ウォームアップ (7分 疾走 + 3分 easy)×4 5分 クールダウン |
| ファルトレクC (ラン) |
20分 ウォームアップjog (7分 疾走 + 3分 jog)×4 15分 クールダウンjog |
| 自転車ファルトレクD | 10分 ウォームアップ (4分 疾走 + 2分 easy)×5 5分 クールダウン |
10月18日の24時間走が目標。ジョグのペースを上げるためのスピード練習を重視。
クロストレーニング、高頻度の戦略で暑い時期でもスピード練習を継続できるようにという意図です。
ここまでスピードを入れるとロングとの両立は難しいため、ロング走(3時間~)は8月以降に計画してメリハリをつけています。
まとめ
今回は夏のトレーニング成功のコツとして、私が意識していることをお伝えしてきました。
一貫して言えることは、トレーニングを「点」で考えず、連続性の中で考えること。
1回1回の練習で一喜一憂しないで、1週間くらいのスパンでちょうど良い刺激になるよう調整していくこと。
トレーニングは継続性が第一ということです。
夏はパフォーマンスが低下しやすく、下手をすると潰れやすい=練習効果を十分に得られないで終わってしまうリスクが大きい時期です。だからこそ、安定性を高めるための方針(ペースを気にしすぎない、柔軟性、分割)が役に立ちます。
情報量が多くなってしまいましたので、ぜひ3分だけでも時間をとって今回の内容を頭の中で再整理してみてください。
そして、練習メニューなどで具体的に改善してみたいことが見つかったらチャレンジしてみてください。
トレーニングの創意工夫を楽しみましょう。
今日もお読みいただき、ありがとうございました!